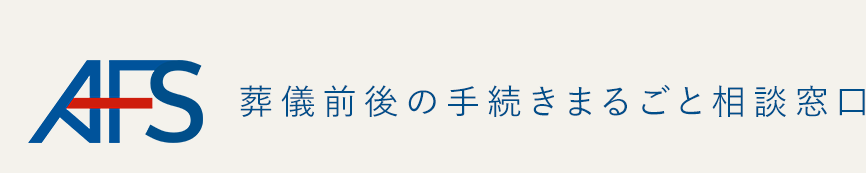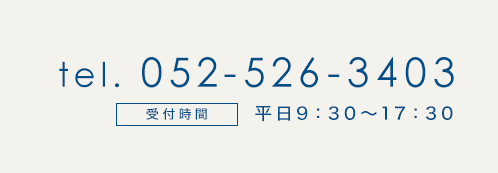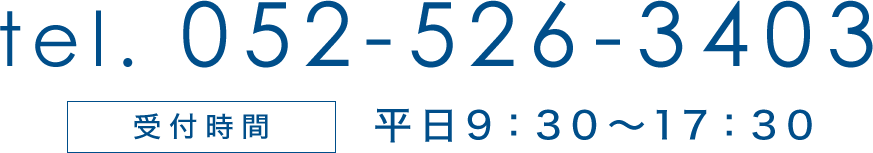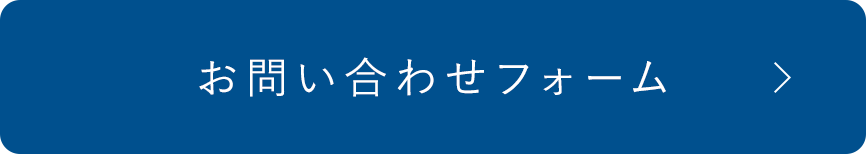空き家になった建物、どうすべきか?

空き家問題は「他人事」ではありません。
近年、日本では高齢化や相続の増加により、使われていない空き家が急増しています。
「実家が空き家になっているけど、手をつけられていない」
「亡くなった親の家を相続したが、どうすればいいのかわからない」
という相談は非常に多く、放置することのリスクが年々注目されています。
放置された空き家のリスクとは?
空き家は“誰も住んでいない建物”であっても、持ち主には管理責任と固定資産税の支払い義務があります。
放置すると次のような問題が発生することも…
| 老朽化による倒壊・瓦落下リスク | 台風・地震時に近隣に被害を与える危険があります。 |
|---|---|
| 犯罪・不法侵入・放火の温床に | 人がいないことで、空き巣や不審者の侵入を招くケースも。 |
| 景観悪化や近隣トラブル | 草木の繁茂やごみの不法投棄などが起きやすく、近隣住民との関係悪化にもつながります。 |
| 行政から「特定空き家」に指定されると… | 行政から指導・勧告・命令を受け、解体命令や重い税負担が課せられる場合もあります。 |
空き家をどうする?選択肢は主に3つ
空き家は、「ただ持ち続ける」のではなく、早めに方向性を決めることが大切です。選択肢は以下の3つ。
| 維持して住む・貸す |
・修繕して自分や家族が住む ・リフォームして賃貸物件として貸し出す |
|---|---|
| 売却する(建物付き or 解体後の更地) | ・不動産として売る場合、老朽化が進んでいれば建物解体後に土地として売るケースも。 |
| 解体して管理する(更地化) | ・解体し、将来の活用に備えておく(駐車場・家庭菜園・売却用地など) |
解体するという選択肢 ― メリットと注意点
| メリット |
◎ 老朽化による倒壊・火災リスクの回避 ◎ 固定資産税が軽減される場合がある (※条件あり。住宅用地の特例を失うこともあるため要確認) ◎ 土地活用の自由度が増す ◎ 売却時に買い手がつきやすい(更地の方が需要あり) |
|---|---|
| 注意点 |
・解体費用は自己負担(家の大きさや構造で100~300万円前後が目安) ・遺品整理や仏壇処分、近隣挨拶など、段取りが必要 ・解体後も「土地の管理責任」は残るため、放置せず草刈りなどが必要 |
解体の流れ(実際にやる場合)
| 【1】建物の現地調査 | 専門業者による建物構造、立地状況、アスベストの有無などを確認。 |
|---|---|
| 【2】見積もり・契約 | 解体費・付帯工事(庭石・塀・浄化槽など)・整地費用などを見積。 |
| 【3】遺品整理・仏壇供養 | 家財を整理し、必要に応じて供養や再利用も検討。 |
| 【4】解体工事・廃棄物処分 | 騒音や粉じん対策を行いながら慎重に作業。廃材は適切に処分。 |
| 【5】整地・完了報告 | 更地にして土地の登記情報を更新するケースも。 |
| 【6】固定資産税や土地活用の見直し | 更地になることで税額が変わるため、税務署や市区町村と確認を。 |
補助金や優遇制度はある?

地域によっては、空き家の解体や活用に対して補助金制度を設けている自治体もあります。たとえば…
・老朽空き家の除却費用補助
・若者や移住者向けに更地活用するための助成
・特定空き家に指定される前の対応で支援を受けられる制度 など
まずは、地元の市区町村役場や不動産相談窓口に相談することが第一歩です。
あとがき
解体とは、思い出を壊す行為ではありません。
むしろ「家族の未来の安心のため」「次の活用に向けた準備」としての前向きな一歩です。
「いつかやらなければ…」が、「今やってよかった」と思える日が必ず来ます。
感情に向き合いながら、時間をかけて検討することが何より大切です。